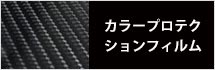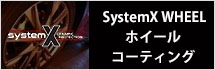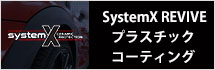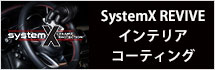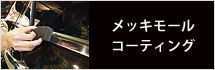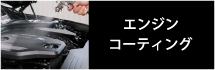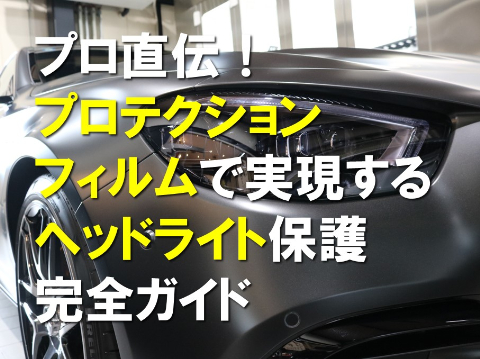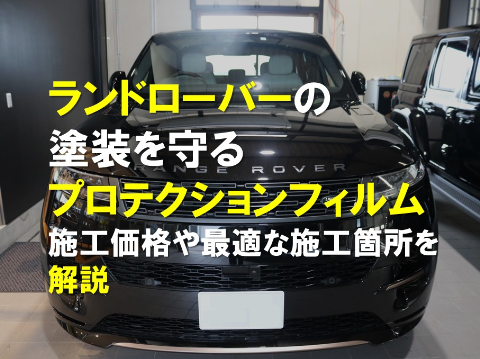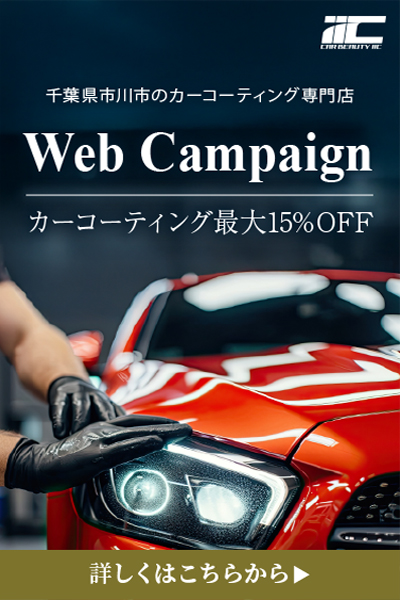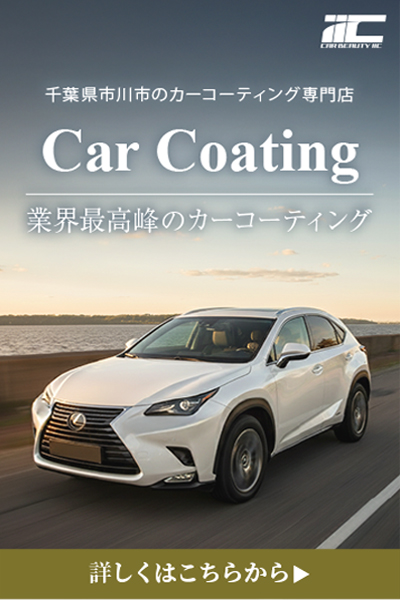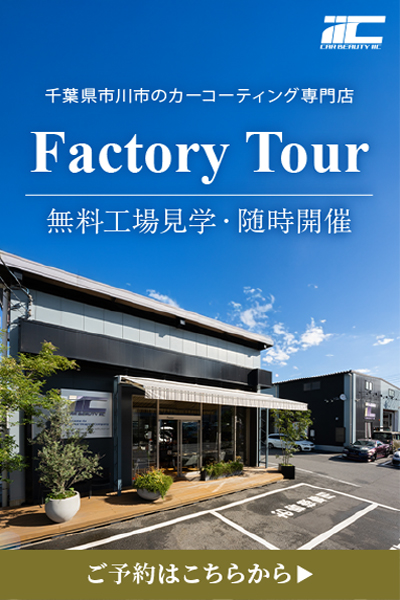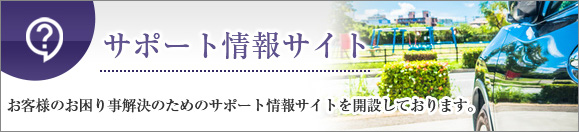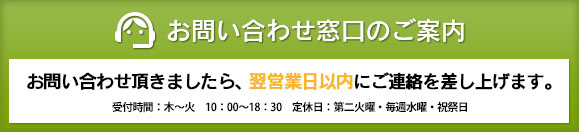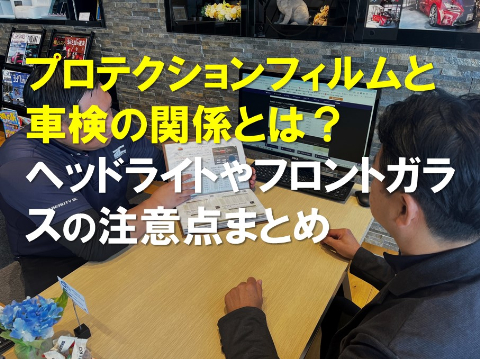
プロテクションフィルムは、飛び石や擦り傷といった物理的ダメージのほか、紫外線や汚れから愛車を守るための保護材です。カラーフィルムを活用すれば、外観のドレスアップも可能で、保護と見た目を両立できる点が特徴です。
ボディだけでなく、ヘッドライトやフロントガラスに施工するケースも増えていますが、そこで気になるのが「車検への影響」です。特に光量や視界に関わる部位では、道路運送車両法に基づく保安基準を満たす必要があります。この記事では、プロテクションフィルムと車検の関係について、注意すべきポイントを具体的に解説していきます。
【結論】プロテクションフィルムの施工は基本的に車検に影響しない

結論から述べると、プロテクションフィルムの施工は基本的に車検には影響しません。冒頭でも触れたように、ヘッドライトやフロントガラスなど視認性や照度に関わる部位には、道路運送車両法に基づく保安基準が設けられています。しかし、2025年7月時点では、プロテクションフィルムの施工がこれらの基準に明確に違反するケースはほとんどありません。
ただし、すべてのケースで安心とは言い切れず、施工部位によっては基準を満たしていないと車検に通らない場合もあります。次の章では、特に注意が必要な箇所や判断基準について詳しく解説していきます。
ボディへのプロテクションフィルム施工は車検への影響はなし

ボディへのプロテクションフィルム施工については、2025年7月時点で道路運送車両法における保安基準上、明確な規制は設けられていません。そもそも車検でチェックされる保安基準は、安全装置や灯火類、視界、排気ガスなど機能面が中心であり、ボディの塗装やデザインに関する規定は存在しないのが実情です。
たとえば、車幅や高さに影響しない範囲でのカラーチェンジや装飾は自由度が高く、検査の対象にはなりません。そのため、カーボン調フィルムやマット調フィルムなど、見た目を大きく変える施工であっても車検に影響することは基本的にありません。ボディ部分に関しては、プロテクションフィルムの施工によって車検に落ちる心配はないといえるでしょう。
ヘッドライトへのプロテクションフィルム施工と車検への影響

プロテクションフィルムの施工箇所の一つに、ヘッドライトがあります。透明タイプは飛び石や紫外線による劣化を防ぎ、黄ばみの進行を抑える効果も期待できます。なかには薄くスモークがかった製品もあり、シャープな印象を演出することも可能です。
ただし、ヘッドライトは照度や色味に関する保安基準が定められており、施工方法によっては車検に通らないおそれもあります。ここでは、その基準と注意点を詳しく解説します。
ヘッドライトに関する保安基準
ヘッドライトに関してプロテクションフィルム施工と特に関係するのは「前照灯の光量」に関する保安基準です。道路運送車両の保安基準 第32条第1項に基づき、前照灯は「夜間、前方40メートルの障害物を確認できる照度を有すること」とされています。
これをもとに、国土交通省の告示(保安基準の細目)では、ロービームの場合、前方25m地点で6,400カンデラ以上の明るさが必要です。この基準を下回ると「光量不足」として車検に通りません。
透明なプロテクションフィルムであっても、厚みや素材によっては光の透過率が下がることがあり、実際の照度が基準を割り込むと不適合と判断されます。とくにスモーク系や着色タイプは光量低下のリスクが高いため注意が必要です。
施工する際の注意点
前述のとおり、ヘッドライトのプロテクションフィルム施工によって光量が保安基準を下回ると、車検に通らない可能性があります。ただし、主要なフィルムメーカーはこの基準を十分に認識しており、多くの製品は光量基準を満たすように設計されています。そのため、信頼できるメーカー品を使用し、施工店の推奨に従えば基本的に問題はありません。
一方で注意が必要なのが、フィルムを貼る前のヘッドライトの状態です。すでに長年使用され、黄ばみが進行している場合、スモーク系フィルムを貼ることで光量がさらに落ち込み、基準を下回るおそれがあります。また、過去に磨きをかけすぎてレンズ表面が傷だらけになっているケースも要注意です。こうした場合は、事前にしっかりと研磨・再生処理を行ってから施工することが望ましいといえます。
フロントガラス用プロテクションフィルムの車検への影響

プロテクションフィルムの施工箇所は、これまでボディやヘッドライトが中心でしたが、近年では飛び石によるヒビ割れ対策としてフロントガラス用の製品も登場しています。
紫外線カットや熱遮断の効果を持つ製品もあり、利便性は高い一方で、フロントガラスは視界確保に直結するため、保安基準の制約が厳しくなっています。ここでは、フロントガラスにフィルムを施工する際に理解しておくべき基準と注意点について解説します。
フロントガラスに関する保安基準
フロントガラスに関しては、道路運送車両の保安基準 第29条および、告示「保安基準の細目を定める告示」第2章2-1-21により「運転者の視野を妨げないこと」「可視光線透過率が70%以上であること」が定められています。この「可視光線透過率70%以上」という数値は、プロテクションフィルム施工において特に重要なポイントです。
たとえ透明に見えるフィルムでも、わずかな厚みや色味によって透過率が70%を下回れば、保安基準違反となり車検に通りません。透過率はガラス本体とフィルムの合計値で判断されるため、もともと基準ギリギリの車両ではリスクが高まります。ちなみにこの基準は、ガラスの内側に貼るカーフィルムにも同様に適用されており、施工方法にかかわらず可視光線透過率が満たされていることが求められます。
出典:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】〈第一節〉第 39 条(窓ガラス)|国土交通省
施工する際の注意点
フロントガラスに貼るプロテクションフィルムについても、多くのメーカーは保安基準を理解したうえで、透過率70%以上を維持できるように製品を設計しています。ただし、フロントガラス自体の透過率は新車時でもおおよそ70%台であるため、施工後の数%の低下でも基準を割り込むリスクがあります。
とくに、ガラス表面に水垢やシミがある場合や、すでに内側にカーフィルムを貼っている車両では、メーカー製の透明フィルムでも基準を満たさない可能性があります。施工する際は、基準を満たした製品を使っているか、国が定めた専用の測定機器で透過率を測定し、保証書を発行してくれる店舗を選ぶことが重要です。また、フィルムは経年で黄ばみが生じるため、施工店が定める交換目安を守って適切に張り替えることも大切です。
市販フィルムやDIY施工で気をつけたいポイント3つ
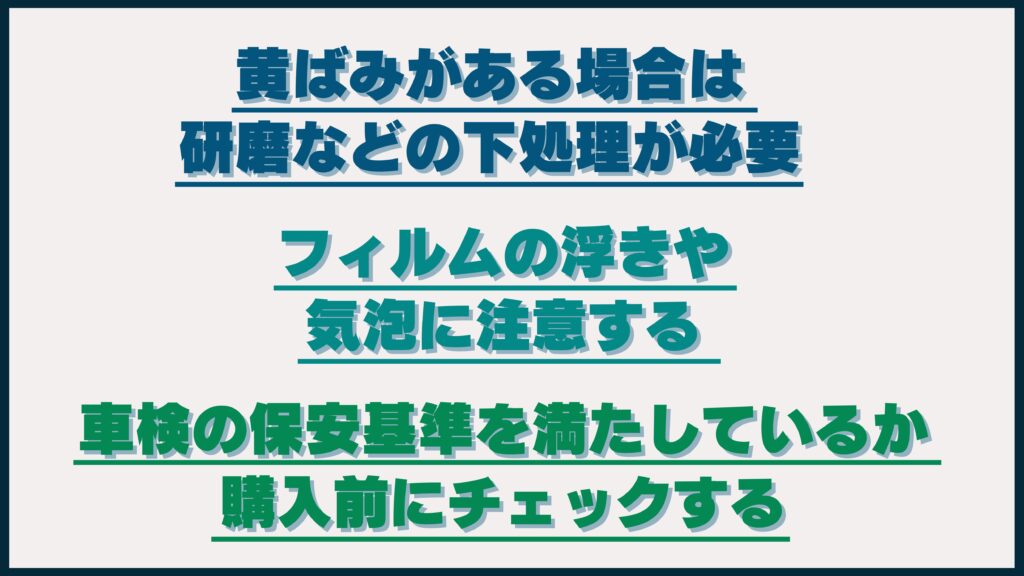
近年は、車種ごとにあらかじめカットされた市販のプロテクションフィルムも登場しており、必要な道具さえそろえれば自分で施工することも可能になっています。
施工費を抑えられるという点で魅力はありますが、品質のバラつきや施工精度によっては、車検に影響するリスクもあるため注意が必要です。ここでは、DIY施工や市販品を使う際に気をつけておきたい代表的なポイントを3つ紹介します。
黄ばみがある場合は研磨などの下処理が必要
黄ばんだヘッドライトやガラスにそのままプロテクションフィルムを貼ると、見た目が悪くなるだけでなく、光量が低下して車検に通らないおそれがあります。黄ばみは紫外線や経年劣化による酸化が原因で、レンズ表面に曇りや微細なひびが生じ、光の透過効率が大きく落ちます。そこにフィルムを重ねると、さらに光量が下がるため注意が必要です。
対策としては、施工前にヘッドライトを研磨し、本来の透明度を回復させることが重要です。ただし、市販の研磨剤やキットではムラや傷が残りやすく、途中で断念するケースもあります。確実に仕上げるには、専門店でプロの研磨を受けてからフィルムを施工するのがおすすめです。
浮きや気泡に注意する
DIYでプロテクションフィルムを貼る際に注意したいのが、フィルムの浮きや気泡です。貼り付けが不十分だと、時間の経過とともに端がめくれたり、内部に空気が入り込んで視認性に悪影響を与えたりすることがあります。とくにヘッドライトやフロントガラスは「視界を妨げないこと」という保安基準があるため、気泡が光を乱反射させると車検に通らないおそれがあります。
また、フィルムの浮きが原因で走行中に風を受けて破れたり、剥がれが進行したりすることもあります。こうしたトラブルを防ぐには、貼り付け面を事前に脱脂・洗浄し、ゴミやホコリを完全に除去することが重要です。仕上がりに不安がある場合は、無理せず専門店に依頼するのが安心です。
車検の保安基準を満たしているか購入前にチェックする
市販のプロテクションフィルムを選ぶ際には、必ず保安基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。とくにヘッドライトやフロントガラスに使うフィルムは、透過率や光量への影響があるため、基準を下回ると車検に通りません。
見た目が透明でも、実際の透過率が70%を切っている製品も存在します。注意すべきなのは、安価な海外製やノーブランド品などで、製品に性能データの記載がないものです。「車検対応」と書かれていても、実測値で基準を満たさないケースは珍しくありません。
購入前には、製品の仕様書に可視光線透過率やJIS規格準拠などの表記があるかを必ず確認しましょう。信頼できるメーカーや専門店での取り扱い品を選ぶことが、車検への不安を減らすポイントです。可能であれば施工後の透過率測定を行ってくれる店を利用するとより安心です。
車検を意識したプロテクションフィルム施工のチェックポイント
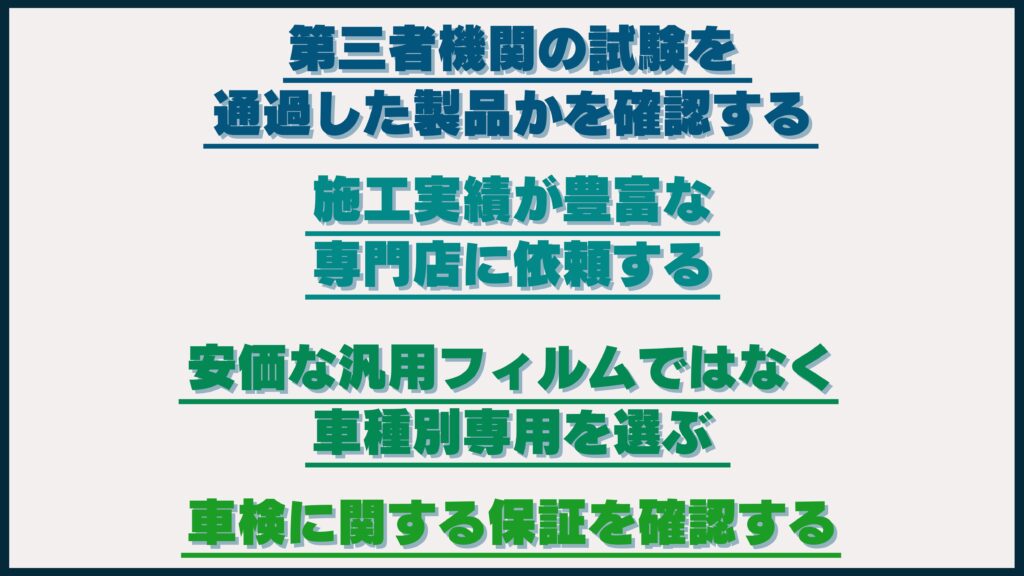
車検は、安全性や法令遵守が確認される公的な検査であり、これに通らなければ公道を走ることができません。プロテクションフィルムが原因で車検に落ちるとなると、貼り直しや再検査の手間・費用も発生し、軽い問題では済まなくなります。
そのため「たぶん大丈夫だろう」といった曖昧な判断で施工するのは非常に危険です。確実に保安基準を満たす状態で車検を通すためには、あらかじめ押さえておくべきポイントがあります。ここでは、その代表的なチェック項目を4つ紹介します。
第三者機関の試験を通過した製品かを確認する
プロテクションフィルムを選ぶ際は、第三者機関の試験を通過した製品かどうかを確認することが重要です。メーカー独自の表示だけでは信頼性に欠け、実際には保安基準を満たさないケースもあります。
特にフロントガラスやヘッドライトに使用する場合は、可視光線透過率や耐候性などについて、JIS(日本産業規格)や自動車技術総合機構などの試験データが公開されている製品を選ぶと安心です。透過率70%以上が実測で確認されている製品であれば、車検でも問題となるリスクが低くなります。製品仕様書や検査証明書の有無を確認し、施工店でもその点を説明してもらうとより確実です。
施工実績が豊富な専門店に依頼する
プロテクションフィルムを施工する際は、実績のある専門店に依頼するのが基本ですが、重要なのはその“実績”の中身です。特にヘッドライトやフロントガラスへの施工経験があり、車検を見据えた対応ができるかが判断の分かれ目です。
国が認可した可視光線透過率の測定器を使用し、施工前後に測定を行っているかも確認しましょう。簡易測定器では、車検時の数値とズレる恐れがあります。
さらに、透過率の変化や不合格の可能性など、リスクを事前に正直に説明してくれる店舗かどうかも重要です。都合のよい情報だけでなく、懸念点まで丁寧に説明する店は信頼できます。公式サイトや口コミを活用して、実態を見極めるようにしましょう。
安価な汎用フィルムではなく車種別専用を選ぶ
市販されているプロテクションフィルムの中には、どの車にも対応できるように作られた汎用品がありますが、車検を意識するなら車種別専用フィルムを選ぶことをおすすめします。汎用タイプは形状が合わず、カットのズレや浮きが出やすく、視界や光量に影響するおそれがあります。
さらに、安い汎用フィルムは素材の品質も低い傾向があり、紫外線や熱によって短期間で黄ばみやひび割れが生じることもあります。そうなると本来の保護性能を発揮できないだけでなく、再施工の手間や費用もかかります。車種別専用フィルムは形状だけでなく性能や耐久性にも配慮されており、長く使ううえでも安心です。価格だけで選ばず、品質と適合性の両面から製品を選ぶことが大切です。
車検に関する保証を確認する
プロテクションフィルムを施工する際は、車検に関する保証があるかどうかも必ず確認しておきたいポイントです。特にフロントガラスやヘッドライトなど、保安基準が厳しい箇所に施工する場合、万が一車検に通らなかった場合の対応を事前に確認しておくことが重要です。
保証の内容は店舗によって異なります。たとえば「車検非適合時は無償で張り替え」「測定結果を基に保証書を発行」といった形で対応している専門店もあれば、あくまで施工のみで保証は行わない店もあります。
単に「車検対応」とうたっていても、実際の保証がないケースもあるため、書面で保証内容を明示してくれるかどうかを必ず確認しましょう。施工店にとって保証は負担の大きい対応でもあるため、その有無が店舗の自信や実績を見極める指標にもなります。
プロテクションフィルムと車検に関するよくある質問

プロテクションフィルムに関係する車検の保安基準などについて解説してきましたが、施工を検討するうえでまだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。最後はプロテクションフィルムと車検に関する、4つのよくある質問に答えていきます。
フィルムが原因で車検に通らなかったらどうなる?
フィルムが原因で車検に通らなかった場合は、基本的に不合格となり、該当箇所のフィルムを剥がしてから再検査を受ける必要があります。再施工やスケジュールの調整が必要になるため、予想外の手間や出費が発生するケースもあります。
なお、この場合に違反点数が付くことはなく、罰金や反則金も科されません。ただし、不合格のまま運転を続けると「整備不良車運行」として行政処分の対象になります。また、再検査は不適合箇所のみの部分検査で済むため、費用は1,000~1,500円程度に抑えられます。事前に測定や保証をしてくれる施工店を選んでおけば、こうしたリスクを大幅に減らせます。
黄色のヘッドライトフィルムは車検に通る?
黄色いフィルムを貼ったヘッドライトは、条件によっては車検に通る場合もあります。ただし、色だけでなく光量や配光も審査対象であり、すべての条件を満たしていないと不合格になります。
道路運送車両の保安基準では、前照灯の色は「白色または淡黄色」とされていますが、「淡黄色」の明確な定義がなく、検査官の判断に委ねられる部分があります。特に最近のLEDヘッドライトはもともと白色が基準であり、黄色い光は違和感を与えやすいため注意が必要です。
加えて、フィルムを貼ることで照度が下がると、光量不足で不適合になるリスクが高まります。安全面や審査通過の確実性を考慮すると、あえて黄色にするのはおすすめできません。
プロテクションフィルムって違法?
プロテクションフィルムそのものは違法ではなく、道路運送車両法上も明確に禁止されているわけではありません。実際、透明で高透過率のフィルムは、保護目的で多くの車に施工されています。ただし、「どこに、どんな状態で貼るか」によっては違法扱いになる可能性があります。
たとえばフロントガラスに貼ったフィルムが透過率70%を下回れば、車検には通らず、使用を続ければ整備不良車運行とされることもあります。また、灯火類にカラーフィルムを貼って色が変わると、保安基準違反になる場合もあります。そのため、お店選びが重要といえます。
ヘッドライトにスモークを貼った場合は違法?
スモークフィルムを貼ったヘッドライトでも、保安基準を満たしていれば車検に通る可能性はあります。ただし、条件は非常に厳しく、前照灯の色は「白色」に限られており、スモークによって色が変化すると不適合と判断されることがあります。
また、明るさについても「ロービームで6,400カンデラ以上」が必要とされており、透過率が下がることでこの基準を下回ると車検には通りません。スモークタイプは特に照度低下が大きく、全面に貼るのは避けた方が安全です。
さらに、2015年9月以降はロービームのカットオフラインが目視で確認できることも検査項目に加わっており、照射状態に影響を与えるような施工は避けるべきです。基本的にはドレスアップ目的ならごく一部に留めるのが無難です。
プロテクションフィルムと車検の関係についてのまとめ

プロテクションフィルムは、飛び石や紫外線などから愛車を守る保護材として広く活用されており、ボディやヘッドライトなどを中心に多くの車に施工されています。基本的に施工によって車検に通らなくなることはありません。
ただし、ヘッドライトに貼る場合は照度や光色に関する保安基準を満たす必要があり、フロントガラス用のフィルムは可視光線透過率70%以上という明確な数値基準が設けられています。状態や貼り方によっては不適合となるケースもあるため注意が必要です。
施工時には、信頼できる専門店で保安基準を確認しながら、車検対応の製品を選ぶことが大切です。ルールを守りつつ、プロテクションフィルムの効果とドレスアップを安心して楽しみましょう。

著者情報
株式会社カービューティーアイアイシー
代表取締役社長 舊役 哲史
2008年にガラスコーティング専門店の株式会社カービューテイーアイアイシーに入社
現在まで2,000台以上のカーコーティング,ガラスコーティングの施工実績を持ち、特に輸入車などの施工実績が豊富である。カーコーティングのオプション作業としてホイールコーティングの実績も豊富で様々な知識と技術力を有す。